【学会発表】日本心理学会第88回大会
熊本で開催された日本心理学会第88回大会で研究報告を行いました。
今回は3つの研究報告を行いました。
1つ目は学部時代にゼミに所属していた北大の院生 白石さんの研究発表で,テーマは「大学生における親への同一視の様相と自己嫌悪感情及び時間的展望の関連について」でした。卒論の内容をまとめたもので,初めての学会発表でしたがたくさんの方に聞きに来ていただき,堂々と質問に答えていました。今後の研究への助言もいただくことができていたようです。
2つ目は子どもの虹情報研修センターの増沢先生が研究代表を務められている子ども家庭庁の科研費に関係する研究で,「虐待重大事例における発生傾向と特徴の探索的検討検証報告書のコーディングに基づく量的分析」というテーマでの発表です。静岡大学の満下先生,志學館大学の白井先生と一緒に発表しました。心理学会なので,虐待のテーマにどれくらい関心を持ってもらえるか... というところでしたが,結構多くの方に足を止めていただけたようでよかったです。
3つ目がようやく自分が主担当した研究で「人はなぜ過酷な環境を目指すのかー南極での探検活動がもたらす価値」というテーマのものです。この研究は静岡大学の村越先生の科研費の助成を受けた研究プロジェクトの一環として行われたもので,南極に越冬隊として行ったフィールドアシスタント(南極でのルート開拓などを行う方たち)を対象にした調査をまとめたものです。
南極はとても美しいところである(らしい)と同時に,死のリスクが高い場所でもあります。特に基地を離れて遠征に出る時にはそのリスクが高まります。そうした危険な経験をしたにも関わらず,多くの人たちがまた南極に行きたいと感じたり,南極滞在はとても素晴らしい経験だったと語ったりします。なぜ,南極での経験は人にそのように肯定的な体験になっているのかについてインタビュー調査で探求しました。この研究で新たに得られた知見としては,彼らは単に南極滞在中にその価値を見出しているのではなく,子どもの頃,あるいは大学生の頃など,ずっと以前に南極に行くことを意識し始めた頃からのさまざまな想いやその人の人生の使命などを抱え,それが南極滞在を通してその人の人生の中に新たな価値となっていたり,大きな転機となり,その後の人生に新たな価値を生み出していることがわかりました。人が危険を冒すということを理解するとき,短いスパンでその理由を説明しようとするのではなく,その人の人生史そのものを理解することによってその意味が理解されるということのようです。
なかなかない研究テーマでしたが,熱心に聞いてくださる方もいらっしゃって,説明しながら改めて研究をまとめなおす視点をもらったように思います。



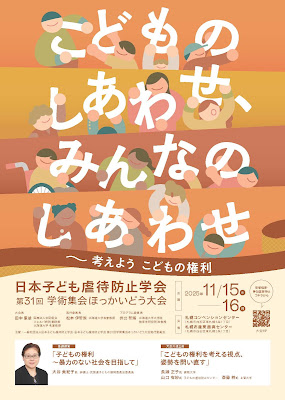

コメント
コメントを投稿